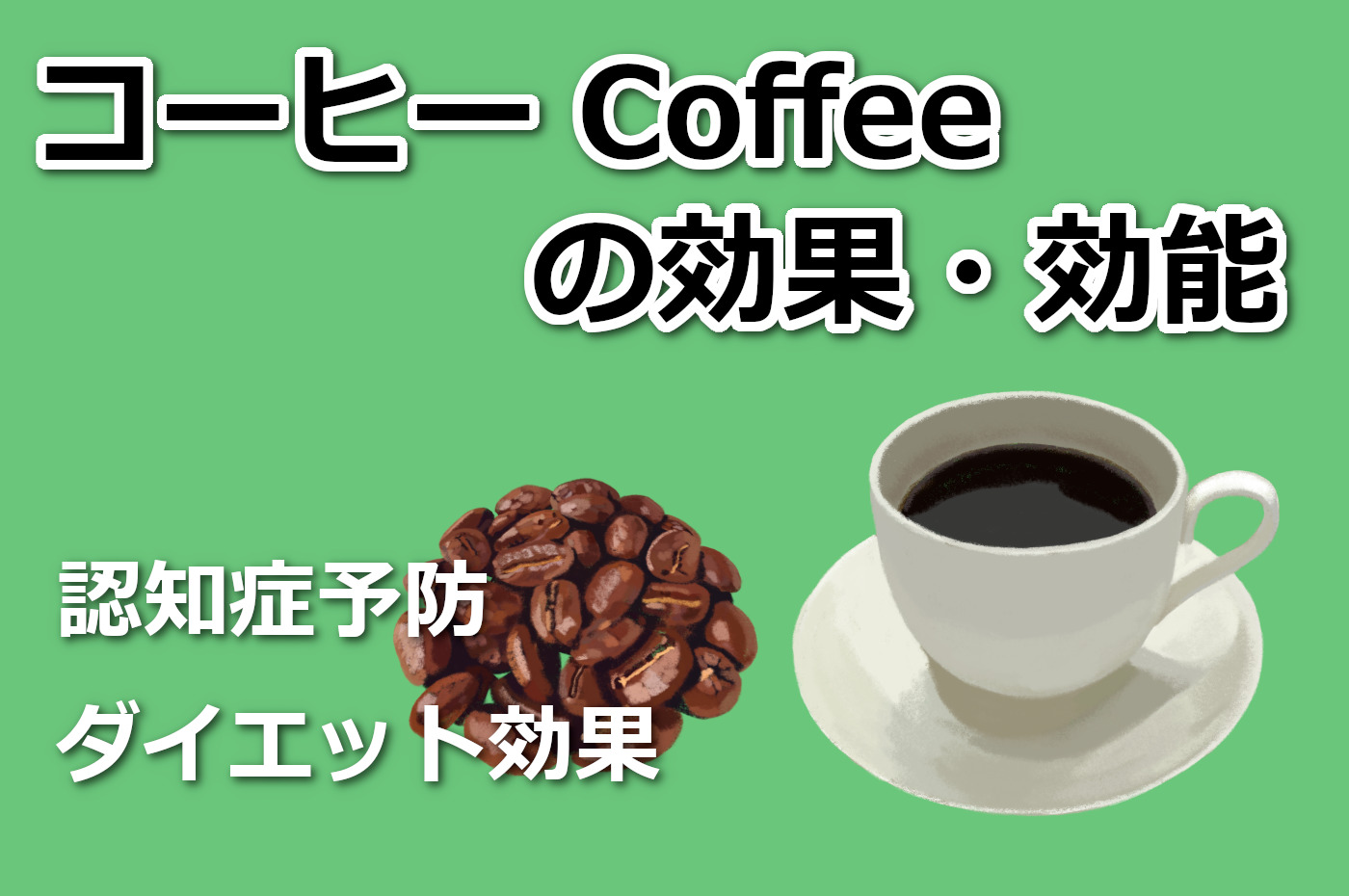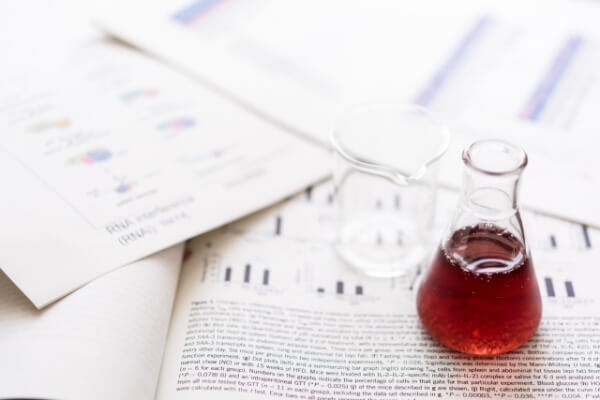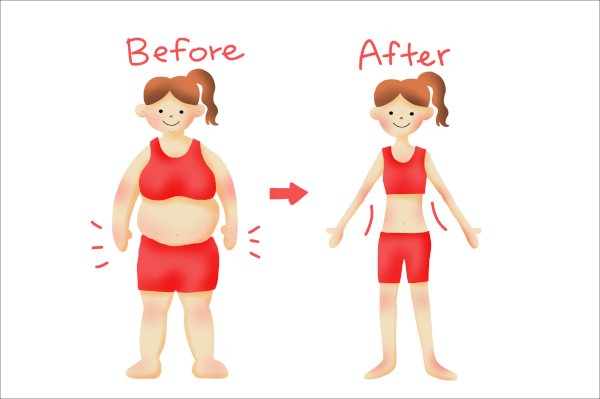コーヒーが健康に良いみたいだけど、どんな効果があるのかな?
このように
- コーヒーの健康効果について詳しく知りたい
- コーヒーの摂取方法が知りたい
など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。

この記事では、コーヒーとは、コーヒーの効果・効能、コーヒーの摂取量、コーヒーの摂取方法、コーヒー摂取しても高血圧にはならない、コーヒーの副作用・摂取する際の注意点、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
コーヒーとは
コーヒーを飲んだことがないという方は少ないのではないでしょうか。
しかし、コーヒーが好きな方でも喫茶店のマスターでない限りはコーヒーについて深く考えたことがある方は少ないでしょう。そこで、おさらいのため、まずはコーヒーについて徹底解説していきます。
コーヒーの概要
コーヒーとはコーヒー豆を焙煎して挽いた粉末を水、または湯で成分を抽出した飲み物です。コーヒーの歴史はまだ浅くコーヒーの登場は14世紀以降といわれています。
歴史としてはお酒やお茶に遅れて登場したものの多くの国で嗜好飲料として愛飲されています。
ブラックコーヒー、カフェオレ、エスプレッソなどさまざまなバリエーションがあるので、愛飲家達を飽きさせることなく人気の嗜好飲料です。
アメリカンコーヒー、トルココーヒー、ベトナムコーヒーなど国の名前がついたコーヒーも多く存在しており、それほどにコーヒーは世界の人々の生活に密接しているのです。
カフェインとは
コーヒーといえばカフェインと答える人が多いほど、カフェインはコーヒーに主要成分です。タンニンやポリフェノールなども多く含まれているのですが、やはり注目されるのはカフェインです。
コーヒーが登場した当初から眠気覚ましや眠気防止、疲労回復などの効果を持つことが注目されていました。その効果はカフェインの覚醒作用に起因するものです。
カフェインには覚醒作用の他にも解熱鎮痛作用、利尿作用、強心作用を示します。そのため、医薬品では鎮痛剤や総合感冒薬の成分として用いられています。
しかし、不眠やめまいなどの副作用もあるために過剰摂取は厳禁です。また、依存性や中毒性、離脱症状もあるために摂取する時には注意が必要です。近年ではカフェインを多く含んだエナジードリンクの飲み過ぎで救急搬送されるケースが多く報告されています。過剰摂取や連日摂取などに気をつけながらカフェインを摂取していきましょう。
コーヒーの種類・品種
コーヒー豆にはさまざまな品種が存在しています。ブルーマウンテンやキリマンジャロなどと聞いたことがある方が多いかと思いますが、これらはブランド名です。
コーヒー豆の品種は大きく分けて2種類になり、「アラビカ種」と「カネフォラ種」の2種類しか存在していません。
アラビカ種とは
コーヒー全体の65%を占めているスタンダードな品種です。酸味を感じることができるという特徴があり、風味も豊かです。
標高1000~2000mの熱帯高地で栽培されているため栽培することが困難な品種であるといえます。みなさんがカフェで飲んでいるコーヒーはほとんどがアラビカ種でしょう。
カネフォラ種とは
コーヒー全体の35%を占めています。アラビカ種と比較して栽培が簡単であるという特徴があります。葉が大きいので1度にたくさんの実がつきます。そのため、1本の木からの生産量が多いのです。
強い苦味があり、香ばしい味わいが特徴です。カネフォラ種はインスタントコーヒーやブレンドコーヒーとして飲まれることが多いという特徴もあります。
コーヒーの効果・効能
コーヒーには、カフェインやポリフェノールが含まれており、さまざまな健康効果を示します。
ではそのコーヒーには、どのような効果・効能があるのか。研究や臨床結果などによるコーヒーの科学的根拠(エビデンス)を見てみましょう。
アルツハイマー型認知症の予防効果
アルツハイマー型認知症というのは脳内にアミロイドβタンパク質やタウタンパク質が蓄積することによって発症すると考えられています。
そのため、アミロイドβタンパク質やタウタンパク質をいかに蓄積させないかがアルツハイマー型認知症を予防するための鍵だということです。
【アメリカ】フロリダ大学の研究(2009年)
ワーキングメモリーが失われた老齢アルツハイマー病マウスにカフェイン(1日あたり5杯相当)を与えたところ、β-セクレターゼ(BACE1)およびプレセニリン1(PS1)/γ-セクレターゼが活発になり、アミロイドβの蓄積が海馬で40%減、皮質で46%減が抑制されたことにより、アルツハイマー病の予防効果の可能性が示唆されました。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19581722
パーキンソン病の予防効果
コーヒーにはパーキンソン病を予防する効果もあります。パーキンソン病とは簡単にいうとドパミンが不足するために起こる疾患です。
【カナダ】モントリオール総合病院の研究(2012年)
日中に眠気の症状があるパーキンソン病(PD)患者61人のうち31人をプラセボ、30人をカフェイン無作為に割り当て、カフェインを1日2回100mgを3週間、その後1日2回200mgを3週間摂取させたところ、CGI-C、Epworth睡眠スケールスコア、PDスケールスコアに改善が見られたことから、カフェインにパーキンソン病予防効果が示唆されました。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22855866
【日本】東京福祉大学の研究(2017年)
実際にコーヒーがパーキンソン病を予防する効果があるのかを確かめる実験も行われています。その結果、コーヒーに含まれているカフェインにはドパミン神経細胞を保護する効果があることがわかりました。また、コーヒーに含まれているポリフェノールの一種であるクロロゲン酸にもパーキンソン病に関与する分子であるα-シヌクレイン毒素を軽減することがわかり、これら2つの働きによってパーキンソン病を予防します。
出典:https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/11747/1/%E7%B4%80%E8%A6%81_Vol8-1_1-1kuribara%E3%80%803-13.pdf
出典:http://coffee.ajca.or.jp/webmagazine/health/doctor/80health
糖尿病の予防効果
コーヒーには糖尿病のリスク低減させる予防する効果もあります。 実験を行った結果、コーヒーを飲む習慣がある人の方が糖尿病のリスクが低減されました。
【オーストラリア】シドニー大学の研究(2009年)
18件の研究45万7922人の参加者データから報告されました。1日に消費されるコーヒーを1杯追加するごとに糖尿病の過剰リスクの相対リスクが7%減少することがわかりました。さらに1日0~2杯飲むに比べて1日3~4杯飲む人は糖尿病リスクがおおよそ25%減少しました。これによりコーヒーの消費とその後の糖尿病のリスクとの間の逆対数直線関係を見出した。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20008687
【日本】国際医療研究協力推進協会の研究(2009年)
40〜69歳の合計55,826人の被験者(男性24,826人、女性31,000人)を10年間追跡し、アンケート結果に基づいて心理的要因と糖尿病を評価した。10年間の追跡調査期間中に、男性の糖尿病の1,601例(6.4%)および1,093例(3例)が記録された。女性の5%)糖尿病のリスクは、特に男性の間で、ストレスレベルが上がるにつれて高まりました。低ストレスと比較した高ストレスの多変量調整オッズ比は、男性で1.36、女性で1.22であった。糖尿病のリスクは、女性の間でのみA型行動のレベルが上がるにつれて高まりました。低レベルのA型行動と比較した高レベルのA型行動の多変量調整オッズ比は、男性で1.09、女性で1.22であった。特に男性において、知覚される精神的ストレスと糖尿病の発生率との間に関連性を見出した。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19270421?dopt=Abstract
がんの予防効果
コーヒーは大腸がんと肝がんのリスクを低減するという可能性が示唆されています。
【日本】国立がんセンターがん予防検診研究センターの研究(2005年)
HCC患者(男性250人および女性84人)は、90,452人の中年および高齢の日本人被験者(43,109人の男性および47,343人)からなる10年の追跡調査から特定されました。毎日またはほぼ毎日コーヒーを飲む被験者(男性と女性を合わせたもの)は、ほとんどコーヒーを飲まなかった人々よりもHCCリスクが低かった0.49。リスクは消費されたコーヒーの量と共に減少しました。この人口のほとんど飲酒者における肝癌のリスクは、10年間で10万人当たり547.2ケースであったが、毎日コーヒーを飲んでいる10万人当たり214.6ケースであった。これにより日本人では、習慣的なコーヒーを飲むことでHCCのリスクが低下する可能性が示唆されます。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15713964?dopt=Abstract
ダイエット効果
コーヒーに含まれているカフェインには体内の熱産生を促して脂肪の燃焼を促す効果があることがわかっています。
【日本】東京農業大学の研究(2005年)
マウスを用いた実験によって、カフェインを摂取すると褐色細胞からの熱放出が増加するという報告がされています。体内のエネルギーを熱として放出するために体脂肪を蓄積を減少させたことを示唆します。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16306706
冷え症の改善効果
コーヒーに含まれているカフェインには手足などの末梢血管を拡張する働きがあります。
【コロンビア】ボゴタ大学の研究(2009年)
末梢血管が拡張して血流が良くなることによって冷え性に改善に期待ができます。また、コーヒーを飲むことによってカフェインの摂取だけでなく、香気成分とのシナジー効果によって冷え性を改善していきます。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19061970
カフェインの覚醒効果
コーヒーにはカフェインが含まれており、眠気防止として役立つことは有名です。カフェインには覚醒作用があるために睡眠を抑制して脳を活性化させることで眠気覚ましになるということがわかっています。
【日本】東京福祉大学の研究(2015年)
脳には睡眠を促す神経伝達物質を受け取る受容体が多く存在しています。カフェインはその受容体に50%ほどと結びついてしまうので、覚醒してしまいます。
出典:https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/10162/1/%E7%B4%80%E8%A6%81Vol6-2_p109-1-1_kuribara.pdf
コーヒーの摂取量
コーヒーの健康効果がわかったところで、1日どのくらいコーヒーを飲めば良いのでしょうか?当然、飲み過ぎてしまえば体に悪影響を与えてしまいます。そこでコーヒーの摂取量について解説していきます。
カフェインの最大摂取量は1日400mg
欧州食品安全機関では、成人が摂取しても体に影響がない1日のカフェイン量を設定しており、成人の場合には1日カフェイン400mgであれば、体に影響がないとされています。
コーヒー1杯が150mlとして、おおよそ80mgのカフェインが含まれています。すると、1日5杯までであれば、何の問題もなくコーヒーを摂取することができるということです。 この摂取量も目安にコーヒーを飲みましょう。
コーヒーの摂取方法
コーヒーにはさまざまな飲み方が存在しています。健康面を考えた場合の最高の飲み方をご紹介します。
【1】ブラックコーヒーで飲む
健康効果を期待してコーヒーを飲むのであれば、シンプルですがブラックコーヒーがおすすめです。砂糖やミルクを入れてしまうと、1日に何杯もコーヒーを飲む場合には糖質を摂り過ぎてしまいます。
脂肪を燃やすことを目的にコーヒーを飲もうと思っている方は、砂糖やミルクの入れすぎで、逆に太ってしまう可能性さえあります。
【2】ホットコーヒーで飲む
また、アイスとホットであれば、ホットコーヒーがおすすめです。ホットコーヒーの方が体を冷やさないので、冷え性の改善を目的にコーヒーを飲むのであればホットコーヒーを選びましょう。
しかし、コーヒーに含まれているクロロゲン酸は熱に弱いという特徴があります。あまりに高温のお湯でドリップしてしまうとクロロゲン酸の効果が薄れてしまいます。
そのため、80℃くらいのお湯でドリップするとクロロゲン酸も壊さず、体も冷やさずに最も効果的にコーヒーを飲むことができます。
コーヒー摂取しても高血圧にはならない
コーヒーにはカフェインが含まれていることから摂取後に血圧が上昇します。そのため高血圧になると考えられてきましたが、近年の研究により、コーヒーと高血圧の関連性がないことがわかっています。
【スペイン】マドリード自治大学の研究(2011年)
5つの試験において、200〜300mgのカフェインの投与したところ、収縮期血圧において8.1mmHgおよび拡張期血圧5.7mmHgの平均増加が生じた。血圧の上昇は、カフェイン摂取後の最初の1時間で観察され、3時間以上持続しました。長期的な2週間の3つの研究ではコーヒーの後、高血圧者の血圧の増加は認められませんでした。また習慣的なコーヒー消費と心血管疾患のより高いリスクの間の関連の証拠を全く見つけませんでした。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21880846
高血圧者がコーヒー3杯飲んでも上の血圧上昇は8.1mmHgです。これは私たちが食事をして血圧が上がるのとほぼ同じであるためコーヒーの影響によって高血圧になるのは低いと考えられます。
| 高血圧者のコーヒー摂取 | |
| 約3杯摂取 3時間後まで |
+8.1mmHg |
| 1日3~5杯を 2週間摂取(安静時) |
変化なし |
| 日常活動 | |
| 会議 | +20.2mmHg |
| 通勤 | +14.0mmHg |
| 歩行 | +12.0mmHg |
| 食事 | +8.8mmHg |
| 会話 | +6.7mmHg |
| 書き物 | +5.9mmHg |
| 安静時 | 0.0mmHg |
| 睡眠 | -10.0mmHg |
万が一、気になる方はカフェインが一切入っていないカフェインレス(ノンカフェイン)コーヒーを飲むことをおすすめします。
コーヒーの副作用・摂取する際の注意点
覚醒作用があるので飲む時間帯に気を付ける
コーヒーはさまざまな健康効果がありますが、飲み方を間違えてしまうと生活に支障が出てしまう可能性があります。最も気をつけなければならないのは、コーヒーの覚醒作用です。
夜の時間帯にコーヒーを飲んでしまうと、脳が覚醒してしまい夜の睡眠を妨げてしまう可能性があります。時間帯に注意してコーヒーを飲みましょう。
仕事をしている方であれば、コーヒーを摂取することによって脳を覚醒させて仕事のパフォーマンスを向上させることも可能です。
そのため、朝コーヒーを飲んだり昼休憩にコーヒーを飲んだりするのは体に良い影響を与えますので、コーヒーを飲むのは15時までにしましょう。
15時までであれば、夜の睡眠に悪影響を与えずに昼間の時間帯の眠気を防止することができます。
コーヒーの過剰摂取は要注意
また、コーヒーを過剰摂取してしまうと依トイレが近くなる、落ち着きがなくなる、胃や腸の調子が悪くなる、頭が回らなくなる、夜眠れなくなるなどの症状が引き起こされ体に悪影響を与えてしまいます。
このような症状が出てきたらコーヒーの摂取量が過剰になっていないかチェックしましょう。 コーヒーの依存性は軽いといわれていますが、注意するに越したことはありません。
毎日コーヒーを飲んでいる方がコーヒーを飲むのを止めるとだるさ、頭痛、嘔吐、集中力の欠如などの症状が現われることがあります。
徐々にコーヒーの摂取量を減らしていけば、このような症状は現われにくくなります。そのため、コーヒーの飲み過ぎには気をつけて、これまでコーヒーを飲んでいる方が急にコーヒーをやめることは避けましょう。
カフェインレスコーヒーを効果的に摂取する
コーヒーの過剰摂取が気になる方は、カフェインが全く入っていない「カフェインレスのコーヒー」や、カフェインを極力減らした「デカフェのコーヒー」を飲むという選択もあります。
これらのコーヒーを活用していくとさらに効果的にコーヒーを摂取することが可能になります。 夜の睡眠に影響が出てしまうことが不安な方は、15時までは普通のコーヒーを飲んでそれ以降はカフェインレスやデカフェのコーヒーを飲めば良いでしょう。
現代では、健康に特化したさまざまなコーヒーが販売されているので、自分の生活に合わせて活用していきましょう。
おわりに
今わかっているだけでも多くの健康効果あるコーヒーですが、これからも研究者たちによってさらなる可能性が実験によって明らかになることでしょう。
コーヒーをメリット、デメリットを理解して上手く活用すれば健康な生活を手に入れることは可能です。
覚醒作用、依存性、中毒性などデメリットもありますが、これらをしっかりと理解しておけば生活に悪影響を与えずに健康生活を送れることでしょう。
これまでコーヒーを飲む習慣がなかった方は、過剰摂取に気をつけながら少しずつコーヒーを生活の中に取り入れていきましょう。