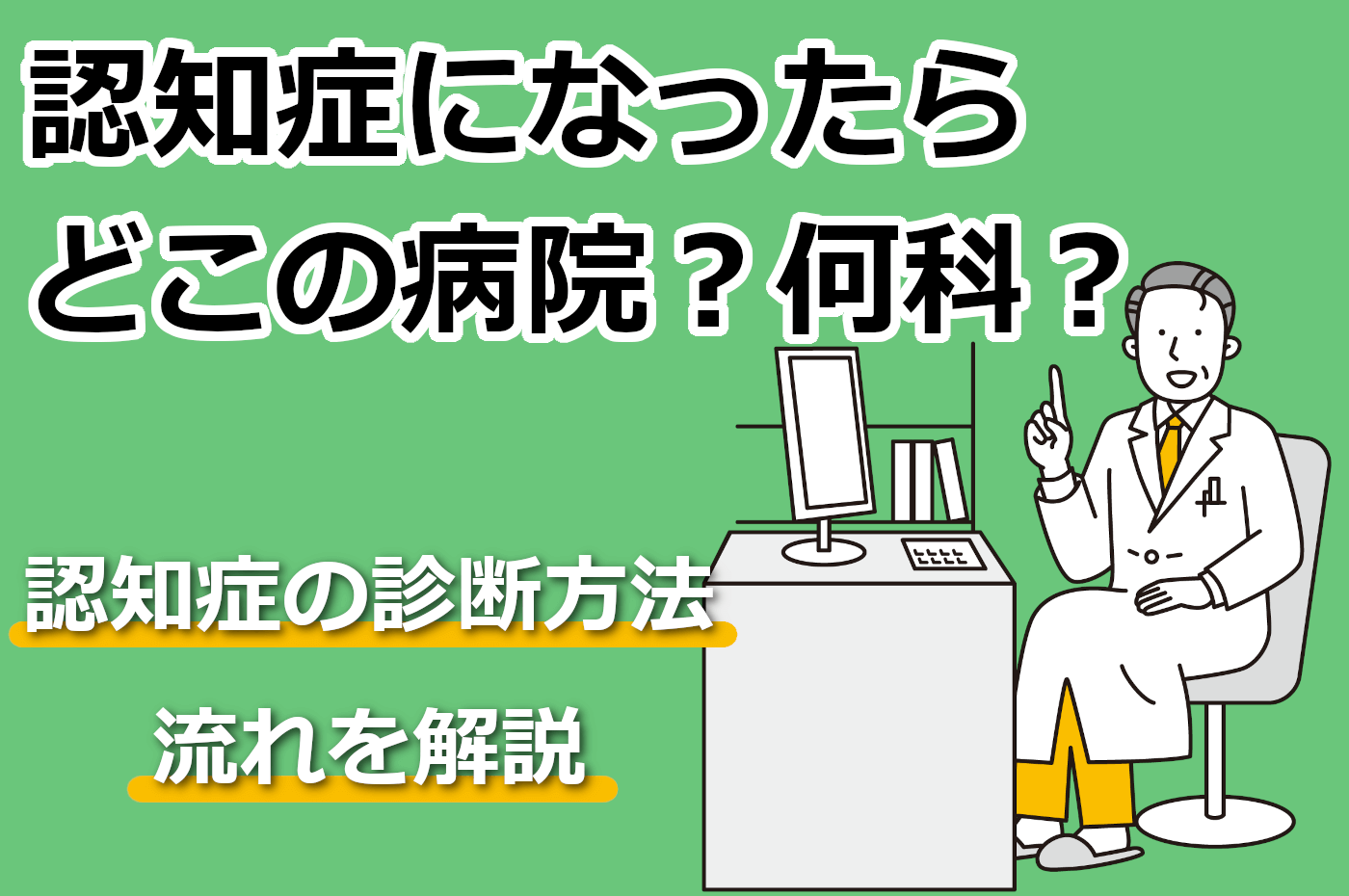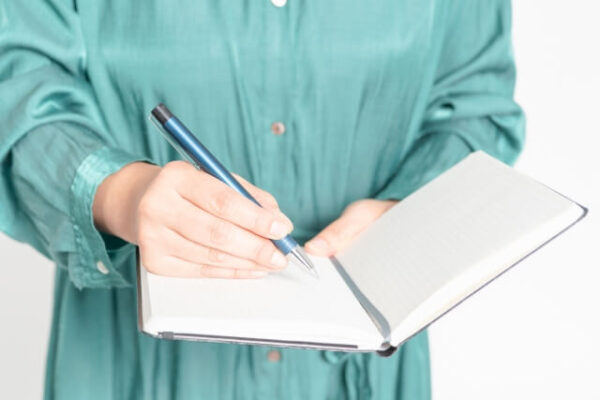「最近、物忘れが多い気がする…」「家族の様子が少し心配…」
もしかして認知症? そう感じたとき、適切な病院で診断を受けることが、ご本人やご家族にとって大切な第一歩となります。
しかし、いざ病院に行こうと考えても、以下のような疑問や不安が先に立つのではないでしょうか。
- 認知症の相談は何科を受診すればいいの?
- どこの病院が専門的に診てくれる?
- 認知症と診断されるのが怖い
- 治るの?薬で進行を止められる?
- 本人が受診を嫌がったらどう説得する?

この記事では、「認知症かもしれない」と感じたときに、どこの病院・何科に受診すればよいのか、受診前に何を準備すべきか、検査の流れや費用、本人が受診を嫌がる場合の対処法まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、認知症に関する病院受診の疑問や不安が解消され、適切な第一歩を踏み出すことができるはずです。ぜひ最後までお読みください。
まずは「かかりつけ医(主治医)」へ相談
認知症の不安を感じたとき、まず身近な「かかりつけ医(主治医)」に相談すべきか、それとも直接「認知症専門の病院(何科?)」へ行くべきか、迷う方も多いでしょう。

結論から言うと、まずは「かかりつけ医(主治医)」に相談するのがおすすめです。
普段からあなたの健康状態をよく知るかかりつけ医は、ささいな変化にも気づきやすく、認知症の初期サインかどうか判断する上で重要な情報を持っています。高血圧や糖尿病など、他の持病との関連も考慮した上で、適切なアドバイスをしてくれます。
かかりつけ医には
- 最近物忘れが多い
- うつ状態である
- 不安が強いことがある
- 場所がわからないことがある
- 以前よりも怒りっぽい
など、具体的な症状を伝えましょう。

かかりつけ医がその情報をもとに適切な専門医(精神科、脳神経内科、もの忘れ外来など)がいる病院を紹介してくれます。その際、「紹介状」を書いてもらうことで、専門病院での診察がスムーズに進み、これまでの経緯や検査結果などの情報が共有されるため、診断の精度も高まります。
かかりつけ医から紹介される病院へ行くメリット・デメリットは以下の通りです。
- 自分で探す手間が省ける
- 紹介状を書いてもらうので初診料が安くなる
- 次の病院に今まで飲んでる薬を伝える手間が省ける
- あまり評判が良くない病院を紹介される恐れがある
もちろん、症状が急速に進んでいる場合や、明らかに専門的な検査が必要だと感じる場合は、直接認知症の専門医がいる「もの忘れ外来」などを探して受診することも可能です。
日本認知症学会や日本老年精神医学会の認知症専門医が認知症かどうか詳しく適切な診察をしてくれます。

認知症専門医は、認知症についての専門的知識や経験など一定の水準で学会の審査に合格した医師が認定され登録されています。
認知症を診られる診療科一覧と特徴
かかりつけ医(主治医)がいない場合は、現在の症状に合った以下の診療科がある病院へ受診してください。
認知症を診察する診療科は、精神科、脳神経内科、老年科、もの忘れ外来など複数あり、それぞれに特徴や得意分野があります。
ここでは各診療科の違いや、どんな症状の場合にどの科を選ぶのが適切なのかを分かりやすく解説します。あなたに合った病院・診療科選びの参考にしてください。
もの忘れ外来【ワンストップ専門外来】
「もの忘れ外来」は、その名の通り、物忘れや認知症を専門に診療するために設けられた外来です。特定の診療科名ではなく、病院が認知症診療に力を入れていることを示す名称として使われています。
精神科医、脳神経内科医、老年科医など、認知症の専門知識を持つ医師が担当していることが多いです。認知症の診断に必要な検査(問診、神経心理検査、画像検査など)をスムーズに受けられる体制が整っている場合が多いです。
診断だけでなく、治療、ケア、介護保険サービスの利用相談、家族へのサポートなど、認知症に関する様々な問題をワンストップで相談できる窓口としての役割も担っています。
- 認知症の疑いがあり、どこに相談したらよいか分からない方
- 認知症の診断から治療、今後のケアまで、一貫したサポートを受けたい方
- 専門的な検査や診断を効率的に受けたい方
「もの忘れ外来」を設置している病院は増えていますが、まだすべての地域にあるわけではありません。担当する医師の専門分野(精神科系か、脳神経内科系かなど)によって、診療の特色が異なる場合があります。事前にホームページなどで確認するとよいでしょう。予約制の場合が多いので、事前に電話などで確認が必要です。
精神科/神経科【心の症状+薬物治療中心】
精神科は、心の病気全般を専門とする診療科です。認知症に伴う精神症状(うつ、不安、イライラ、幻覚、妄想、徘徊、暴力など)の診断・治療を得意としています。
認知症の進行を抑える薬(抗認知症薬)や、周辺症状(BPSD)を緩和する薬(向精神薬など)の処方・調整に精通しており、うつ病など、認知症と間違われやすい精神疾患との鑑別診断も行います。
心理検査やカウンセリングを通じて、ご本人やご家族の心理的なサポートも行っています。
- 物忘れなどの認知機能低下に加えて、気分の落ち込み、不安、イライラ、幻覚、妄想といった精神症状が目立つ方
- すでに認知症と診断されており、薬物治療による症状のコントロールや調整を希望する方
- 行動・心理症状(BPSD)への対応に困っている方
精神科と聞くと抵抗を感じる方もいるかもしれません。最近では、老年精神医学を専門とする医師も増えています。神経科は、精神科とほぼ同義で使われることもありますが、脳や脊髄、末梢神経、筋肉の病気を広く扱う神経内科とは異なります。病院によって標榜が異なるため、事前に確認しましょう。
心療内科【ストレス起因も視野に】
心療内科は、ストレスなどの心理的な要因が関連して体に症状が現れる「心身症」を主に診療します。
認知症の初期症状が、ストレスによる一時的なもの忘れや集中力低下なのか、それとも認知症によるものなのかを見極める視点を持っています。
うつ病や不安障害など、ストレス関連疾患と認知症との鑑別、カウンセリングなどを通じて、心理的なアプローチも行います。
- 物忘れや意欲低下などの症状が、強いストレスや環境の変化(退職、近親者の死など)の後に現れた方
- 頭痛、めまい、食欲不振、不眠など、身体的な不調も伴っている方
- 精神科への受診に抵抗がある方
すべての心療内科医が認知症の専門的な診断・治療を行っているわけではありません。認知症診療に力を入れているかどうか、事前に確認が必要です。認知症が確定した場合、より専門的な診療科(精神科、脳神経内科、もの忘れ外来など)への紹介が必要になることがあります。
脳神経内科【画像検査・鑑別に強い】
脳神経内科(神経内科とも呼ばれます)は、脳、脊髄、末梢神経、筋肉の病気を専門とする診療科です。
CTやMRIなどの画像検査、神経心理検査、脳波検査、髄液検査などを駆使して、認知症の原因となる脳の病気(アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症など)を診断することを得意としています。
パーキンソン病など、認知症を伴うことがある神経変性疾患の診断・治療も専門です。
認知症と似た症状を引き起こす他の脳神経疾患(脳腫瘍、てんかん、正常圧水頭症など)との鑑別診断に優れています。
- 物忘れに加えて、手足の震え、歩きにくさ、呂律が回らないなどの神経症状が見られる方
- 頭部外傷の既往がある場合や、脳卒中(脳梗塞・脳出血)の経験がある方
- 画像検査などによる詳細な原因検索を希望する方
精神症状(うつ、妄想など)が主体の場合は、精神科の方がより専門的な対応が可能な場合があります。脳神経「外科」とは異なる診療科です(後述)。
脳神経外科【外科的原因の除外】
脳神経外科は、脳や脊髄の病気に対して、主に手術による治療を行う診療科です。
認知症の原因となる疾患の中には、手術によって治療・改善が可能なものがあります(例:慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍など)。脳神経外科は、これらの外科的治療が必要な疾患の診断と治療を専門とします。
頭部CTやMRIなどの画像診断を行います。
- 頭をぶつけた後に、物忘れや歩行障害などの症状が現れた方(慢性硬膜下血腫の疑い)
- 歩行障害(小刻み歩行、すり足)、尿失禁、物忘れの3つの症状(ハキムの三徴)が見られる方(正常圧水頭症の疑い)
- 他の科で、脳腫瘍など外科的治療が必要な疾患が疑われた方
脳神経外科は、主に外科的治療が必要なケースを担当します。アルツハイマー型認知症など、手術適応のない認知症の継続的な薬物治療や管理は、脳神経内科や精神科が担当することが一般的です。まずは脳神経内科やもの忘れ外来を受診し、必要に応じて脳神経外科へ紹介される流れが多いです。
老年内科/老年科【高齢者疾患を総合的に診る】
老年内科(老年科)は、高齢者に特有の病気や健康問題を総合的に診療する科です。
高齢者は、複数の病気(高血圧、糖尿病、心臓病など)を抱えていることが多く、多くの薬を服用している場合があります。老年科では、これらの全身状態や併存疾患、服用薬の影響などを考慮しながら、認知症の診断・治療を進めます。
物忘れだけでなく、食欲不振、体重減少、転倒しやすい、活動量の低下など、高齢者特有の様々な問題をまとめて相談できます。
- 高齢(一般的に75歳以上など)で、物忘れ以外にも複数の病気や健康上の悩みを抱えている方
- 多くの薬を服用しており、薬の副作用や相互作用が心配な方
- 認知症だけでなく、全身の健康状態を総合的に診てほしい方
老年内科を標榜する病院は、まだ数が限られている場合があります。認知症のタイプによっては、より専門的な検査や治療が必要となり、他の専門科(精神科、脳神経内科など)への紹介が必要になることもあります。
受診前に準備しておく5つのこと
認知症の診察をスムーズに進め、医師に正確な情報を伝えるためには、事前の準備が重要です。
- 症状のメモ
- 本人の基本情報と既往歴・服薬歴
- 質問したいことリスト
- 持参するもの
- 可能であれば家族の付き添い
以下の5つの点を準備しておきましょう。ご本人が準備するのが難しい場合は、ご家族がサポートしてあげてください。
症状のメモ
いつから?
どのような症状が、いつ頃から気になり始めたか
例)
半年前くらいから、同じことを聞く回数が増えた
どんな症状?
具体的にどのような物忘れや変化があるか。できるだけ詳しく、具体的なエピソードを記録しましょう例)
・財布をどこに置いたか忘れることが週に2〜3回ある
・料理の手順を間違えるようになった
・慣れた道で迷ったことがある
初期サインのチェックリストを参考に、該当する項目を書き出してみましょう。
症状の変化
時間とともに症状はどのように変化しているか
・悪化しているか
・変わらないか
・良くなったり悪くなったりするか
生活への影響
その症状によって、日常生活(家事、仕事、趣味、対人関係など)にどのような支障が出ているか。
気づいた人
本人自身が気づいているか、家族や周囲の人が気づいたのか。
精神・行動面の変化
イライラ、不安、うつ、妄想、徘徊などの症状があれば、その具体的な内容と頻度、きっかけなども記録します。
メモの形式
手書きのメモでも、スマートフォンのメモ機能でも構いません。箇条書きで整理しておくと、医師に伝えやすくなります。
本人の基本情報と既往歴・服薬歴
基本情報
氏名、生年月日、連絡先、緊急連絡先。
既往歴
これまでにかかった主な病気(高血圧、糖尿病、脂質異常症、心臓病、脳卒中、頭部外傷、うつ病など)。手術歴。
服薬歴
現在服用しているすべての薬(処方薬、市販薬)、サプリメント、漢方薬の名前、用法・用量。お薬手帳があれば必ず持参しましょう。薬の飲み合わせや副作用が認知機能に影響している可能性も考慮するため、非常に重要です。
アレルギー歴
薬や食べ物のアレルギー。
生活歴
職業歴、学歴、家族構成、飲酒・喫煙習慣、食生活、運動習慣など。
家族歴
血縁者に認知症や神経系の病気の方がいるか。
質問したいことリスト
診察時に聞きたいこと、疑問に思っていることを事前にリストアップしておきましょう。診察の限られた時間内で、聞き忘れを防ぐことができます。
以下は例
- 認知症の可能性はどのくらいありますか?
- どのような検査が必要ですか?
- 考えられる原因は何ですか?
- 治療法はありますか?
- 薬は必要ですか?副作用はありますか?
- 日常生活で気をつけることはありますか?
- 介護保険サービスについて知りたいです。
- 今後の見通しはどうなりますか?
持参するもの
- 健康保険証、各種医療証(高齢受給者証、限度額適用認定証など)
- 診察券(再診の場合)
- 紹介状(かかりつけ医などからもらった場合)
- お薬手帳(または服用中の薬そのもの)
- 症状などをまとめたメモ
- 質問したいことリスト
- (あれば)過去の検査結果(血液検査、画像検査など)
- 筆記用具
- (必要に応じて)老眼鏡、補聴器
可能であれば家族の付き添い
ご本人の記憶だけでは、症状や生活状況を正確に伝えるのが難しい場合があります。普段の様子をよく知るご家族が付き添うことで、医師はより多くの情報を得ることができ、診断の助けになります。
ご本人が緊張したり、うまく話せなかったりする場合のサポート役にもなります。医師からの説明をご家族も一緒に聞くことで、病気への理解が深まり、今後の対応について一緒に考えることができます。
付き添いが難しい場合は、事前にご家族がメモに状況を詳しく書いて、ご本人に持参してもらうなどの工夫をしましょう。
これらの準備をしておくことで、診察がスムーズに進み、より的確な診断と適切な対応につながります。
認知症の診断方法・診察の流れ
ここでは、認知症専門外来にかかったときの診断の流れを解説します。
【1】問診
まず、認知症の症状を見極めるために診察を行います。
問診では認知症の疑いがあるご本人またはご家族に、現在までの症状、生活状況、既往歴、家族歴、性格などを詳しく聞き取ります。
ご本人への質問(今日の日付、自分の年齢、簡単な計算など)を通じて、記憶力や見当識なども確認します。
問診では以下のことを聞かれます。
- 認知症を疑う症状
- いつ頃から気になりましたか
- どのように経過していますか
- 当てはまる症状をチェックする
・記憶力の低下
・道に迷う
・気分の落ち込みがある
・怒りっぽくなった
・言葉がスムーズに話せない、、、など - 現在治療中の病気
- 現在までの病歴
- 現在服用している薬
- 現在の生活習慣
- 家族構成
- 家族の中に認知症の方はいますか

気になることはその都度、メモを取り、メモが難しい場合はスマホなどで録音をしておきましょう。
【2】身体検査
血圧測定、聴診などの一般的な身体診察に加え、神経系の異常がないかを調べます。
反射、筋力、感覚、バランス、歩行状態などをチェックし、脳血管障害やパーキンソン病など、認知症の原因となりうる神経疾患の兆候を探します。
【3】血液検査・尿検査
血液検査では、認知症のような症状を引き起こす可能性のある、全身性の病気(甲状腺機能低下症、肝機能障害、腎機能障害、ビタミンB1・B12欠乏症、葉酸欠乏症、梅毒など)がないか、貧血や感染症の有無なども調べます。
尿検査では、尿の中にある特殊なたんぱく質を検出して認知症の診断を行います。
【4】神経心理学検査(認知機能検査)

神経心理学検査は、記憶力、注意力、見当識、言語能力、計算能力、遂行能力などを評価するための質問形式や、図形模写などの検査です。
代表的な検査として、改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)やミニメンタルステート検査(MMSE)などがあります。これらは比較的短時間(10〜15分程度)で実施でき、認知機能の全体的なレベルを把握するのに用いられます。
より詳細な評価が必要な場合は、ウェクスラー成人知能検査(WAIS)や、特定の認知領域(記憶、注意、前頭葉機能など)を詳しく調べる検査が行われることもあります。
【5】脳画像検査
脳の萎縮の程度や部位、脳血管障害(脳梗塞、脳出血)の有無、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症など、脳の形態的な変化を調べるために行われます。
- CT(コンピュータ断層撮影)
放射線を利用しエックス線を体の周囲に当てて体の断面画像を撮ります。短時間で撮影でき、脳出血や脳梗塞、脳腫瘍などの発見に有用です。約5分~15分 - MRI(磁気共鳴画像)
磁石と電波を使い磁場を発生させた筒の中で体の断面画像を撮ります。CTよりも詳細に脳の構造を観察でき、早期の脳梗塞や微小出血、脳萎縮の評価(特に海馬など)に優れています。アルツハイマー型認知症などの診断に重要な情報を提供します。約30分 - SPECT(単一光子放射断層撮影)
少量の放射線入り薬剤を注射し、体内の放射線を検知し画像化します。脳の血流低下の状態を調べることができます。約30分
- PET(陽電子放射断層撮影)
放射性薬剤を注射し、脳内の異常蛋白を画像化します。約30分
参考 認知症検査の種類一覧
【5】バイオマーカー検査
くも膜下出血の疑いがありCT、MRIではわからない場合、背中から脊髄液を採取して調べます。
ベッドに横向きで体を丸めて寝てもらい、背骨の間へ注射し脳髄液を採取し、たんぱく質、細胞数などを検査します。
【6】診断
各種、検査の結果が出ましたら、医師がそれらの情報をもと総合的に診断を行います。
認知症が疑われる、認知症の治療が必要と判断した場合は、今後の治療方針についての説明があります。
その病院にて継続して治療を行えない場合は、近くの医療機関を紹介してくれます。
介護サービスが必要な場合は、地域包括支援センターを紹介してくれます。
認知症検査の費用の目安
認知症の検査にかかる費用は、実施する検査の種類や数、医療機関、保険の適用状況(自己負担割合)によって大きく異なります。あくまで目安として参考にしてください。
初診料・再診料
数百円〜数千円(3割負担の場合)
神経心理検査(HDS-R, MMSEなど)の費用
保険適用で、数千円程度(3割負担の場合)。詳細な検査はより高額になることがあります。
血液検査・尿検査の費用
項目によりますが、数千円程度(3割負担の場合)
脳画像検査の費用
- CT
5,000円〜8,000円程度(3割負担の場合) - MRI
8,000円〜15,000円程度(3割負担の場合、造影剤使用などで変動) - SPECT/PET
保険適用となる場合もありますが、数万円〜十数万円程度と高額になることが多いです。実施可能な施設も限られます。
合計費用の目安
問診、神経心理検査、血液検査、脳画像検査(CTまたはMRI)を一通り行った場合、保険適用(3割負担)で、おおよそ1万円〜3万円程度が目安となりますが、検査内容によってはこれ以上になることもあります。
高額療養費制度
医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」を利用できます。限度額は年齢や所得によって異なります。
事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いが限度額までとなります。詳しくは加入している健康保険組合や市区町村の窓口にお問い合わせください。
その他の費用
紹介状がない場合、初診時に別途「選定療養費」が必要になる大病院もあります(数千円程度)。
診断後の治療(薬代など)や、介護保険サービスの利用には別途費用がかかります。
費用について不安な場合は、事前に医療機関の窓口や、地域包括支援センター、医療ソーシャルワーカーなどに相談してみましょう。
本人が受診を嫌がるときの対処法
認知症の疑いがあっても、「自分は病気じゃない」「病院に行く必要はない」と、ご本人が受診を強く拒否されるケースは少なくありません。
無理強いは関係性を悪化させる可能性もあり、慎重な対応が求められます。ここでは、本人が受診を嫌がる場合の対処法をいくつかご紹介します。
本人の気持ちに寄り添い、理由を探る
なぜ病院に行きたくないのか、その理由を頭ごなしに否定せず、まずはじっくり耳を傾けましょう。「病院は怖い」「病気だと認めたくない」「面倒くさい」「家族に迷惑をかけたくない」など、様々な気持ちが隠れている可能性があります。
本人の不安やプライドを傷つけないように、「心配だから一緒に話を聞きに行かない?」「最近忘れっぽいって言ってたから、念のため診てもらおうよ」など、寄り添う姿勢で伝えることが大切です。
「認知症」という言葉を避ける
「認知症」という言葉に強い抵抗感や偏見を持っている方は少なくありません。初期段階では、「物忘れの相談」「健康診断」「血圧の薬をもらいにいく」など、別の目的を伝える方が受け入れられやすい場合があります。
「最近、頭がすっきりしないみたいだから、脳の健康チェックをしてみない?」「〇〇さん(知人など)も、物忘れの相談に行ったら安心したって言ってたよ」など、ポジティブな表現や第三者の例を出すのも有効です。
かかりつけ医に相談する
普段から信頼関係のあるかかりつけ医がいる場合、まずはご家族だけで相談に行き、状況を説明してみましょう。かかりつけ医から本人に受診を勧めてもらったり、定期健診などのタイミングで自然な形で認知機能のチェックをしてもらったりできる可能性があります。
かかりつけ医から専門医への紹介という形をとることで、本人の抵抗感が和らぐこともあります。
他の病気の検査を口実にする
本人が気にしている他の症状(めまい、頭痛、高血圧、糖尿病など)があれば、その検査や診察を理由に病院へ誘い、その際に認知機能についても相談するという方法もあります。
「血圧の薬をもらいに行くついでに、物忘れのこともちょっと先生に聞いてみようか」といった流れです。
家族や親戚、信頼できる第三者に協力してもらう
配偶者や子どもからの言葉は受け入れなくても、他の家族(兄弟姉妹、孫など)や、親しい友人、ケアマネージャー、民生委員など、本人が信頼している第三者から話してもらうと、素直に聞き入れることがあります。
地域包括支援センターに相談する
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。
本人が受診を拒否して困っている状況を相談すれば、専門職(保健師、社会福祉士、ケアマネージャーなど)が具体的なアドバイスをくれたり、場合によっては訪問して本人に働きかけてくれたりすることもあります。医療機関の情報提供も受けられます。
焦らず、根気強く、タイミングを見計らう
一度断られても、すぐに諦めずに、時間を置いて繰り返し働きかけることが必要な場合もあります。本人の機嫌が良いときや、何か困りごとがあって助けを求めてきたタイミングなどを捉えて、再度話を切り出してみましょう。
ただし、あまりにしつこく説得しようとすると、かえって頑なになってしまう可能性もあるため、バランスが重要です。
無理強いはしない
最終的に本人の意思を尊重することも大切です。無理やり病院に連れて行こうとすると、信頼関係が崩れたり、本人が心を閉ざしてしまったりする可能性があります。
受診が難しい場合でも、ご家族だけで医療機関や地域包括支援センターに相談し、今後の対応や利用できるサービスについて情報を集めておくことは可能です。
受診拒否への対応は、ご家族にとって精神的な負担が大きいものです。一人で抱え込まず、周囲のサポートや専門機関の力を借りながら、粘り強く、かつ本人の気持ちを尊重する姿勢で向き合っていくことが大切です。
認知症の診察を受ける時の注意点
家族が認知症の診察を受ける時に注意しておきたいことをまとめました。
①いつもの生活をメモする
本人が普段どのように生活しているのかをまとめてメモしておくことで診察の時、医師も助かりますし、判断材料になります。
具体的には以下のことをメモしておきましょう。
- 気になる症状
- いつから出始めたか
- 症状が出始めたきっかけ(事故や病気など)
- これまでに進行・悪化した様子の有無
- 現在治療中の病気
- 現在までの病歴
- 服用中のお薬
- 家族として心配していること
②認知症でも悲観しない
認知症と聞くとネガティブな印象を受けがちですが、たとえ認知症の診断が出たとしても、家族は決して悲観したり落ち込んだりせず、温かい気持ちで今まで通りに本人に接しましょう。
おそらく本人が一番落ち込んでいると思いますので、不安を抱えないように、笑顔でおだやかにゆっくりとした口調で「先生がちゃんと治療してくれるから大丈夫だよ」と伝えましょう。
③不安な場合は「セカンドオピニオン」を利用する
今までのような一方的な診断や治療ではなく、あくまでも患者本人や家族が治療方法を決める「インフォームド・コンセント」(説明責任と同意)という考えがあります。
医療の進歩とともにたくさんの治療法があり、
- 病気に対する考え方
- 治療法の違い
- 医療技術
などにも差があります。

家族が認知症と診断され、家族も不安を抱え治療を進めるうえで大切なのは医師との信頼関係です。しかし、診断の結果や今後の治療法に不安や迷いがあるときには、「セカンドオピニオン」として複数の他の専門の医師に意見を聞くなど相談してみましょう。
患者本人が治療法などについて、現在診療を受けている担当医師だけでなく、ほかの医療機関の医師に「第2の意見」を求めることができるシステムです。
認知症の受診や診断に関するよくある質問(FAQ)
認知症の受診や診断に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
最近物忘れがひどいのですが、すぐに病院に行くべきですか?何科がいいですか?
物忘れが続く、以前と違うと感じたら、年のせいと自己判断せず早めに受診を検討しましょう。認知症は早期発見・早期対応が重要です。診療科は「もの忘れ外来」が専門ですが、なければ「精神科」「神経科」「脳神経内科」「老年内科」などが選択肢です。まずはかかりつけ医や地域包括支援センターに相談し、適切な病院や診療科を紹介してもらうのも良いでしょう。
認知症の診断では、具体的にどのような検査をするのですか?
認知症の診断は、一つの検査だけで決まるものではありません。まず医師による問診で症状や生活状況を詳しく伺います。次に、記憶力や判断力を評価する神経心理検査(長谷川式スケールやMMSEなど)を行います。必要に応じて、脳の萎縮や脳梗塞の有無を確認するCTやMRIなどの脳画像検査、他の病気を除外するための血液検査などを組み合わせて総合的に判断します。
認知症の検査や診断には、どのくらいの費用がかかりますか?
費用は検査内容や医療機関によって異なりますが、一般的な問診、神経心理検査、血液検査、脳画像検査(CTまたはMRI)を一通り行った場合、健康保険の3割負担で1万円〜3万円程度が目安です。高額な検査(SPECT/PETなど)を行う場合はさらに費用がかかります。医療費が高額になった場合は高額療養費制度を利用できますので、事前に確認しておくと安心です。
本人が「認知症ではない」と言って病院に行きたがりません。どうすればいいですか?
ご本人の不安やプライドに配慮し、無理強いは避けましょう。「物忘れの相談」「脳の健康診断」など、別の目的を伝えて誘ってみるのも一つの方法です。かかりつけ医に相談し、受診を促してもらう、または定期健診の際に診てもらうことも有効です。ご家族だけで悩まず、地域包括支援センターなどの専門機関に相談し、対応方法を一緒に考えてもらうことも大切です。
認知症の相談は、まずかかりつけ医にしても大丈夫でしょうか?
はい、まずは身近なかかりつけ医に相談することをおすすめします。普段の健康状態を把握しているため、変化に気づきやすく、認知症の可能性があるかどうか判断する助けになります。必要であれば、専門的な検査や診断が可能な病院や「もの忘れ外来」などを紹介してもらえます。紹介状があれば、専門病院での受診もスムーズに進むことが多いです。
近くに「もの忘れ外来」がない場合、どの診療科を受診すればよいですか?
お近くに「もの忘れ外来」がない場合は、症状に合わせて他の診療科を選びましょう。気分の落ち込みや妄想など精神症状が強い場合は「精神科」、手足の震えなど神経症状がある場合や脳の検査を重視したい場合は「脳神経内科」、高齢で複数の持病がある場合は「老年内科」などが候補です。地域包括支援センターに相談すれば、地域で認知症診療に対応している病院を教えてもらえます。
家族が認知症と診断されました。家族としてまず何をすればよいですか?
まずは診断結果を受け止め、医師から病気の種類や進行度、治療方針について詳しい説明を受けましょう。ご本人と今後の生活について話し合う機会を持つことも大切です。同時に、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談し、介護保険サービスの利用申請や利用できるサポートについて情報を集めましょう。家族だけで抱え込まず、公的な支援やサービスを上手に活用することが重要です。
おわりに
認知症は、誰にでも起こりうる病気です。「もしかして?」と感じたときに、適切な行動をとることが、ご本人とご家族の未来にとって非常に重要になります。
認知症に関する不安や疑問は、一人で抱え込まず、まずは勇気を出して専門家へ相談することが第一歩です。かかりつけ医、お住まいの地域の地域包括支援センター、もの忘れ外来などが、身近な相談窓口となります。
早期の気づきと適切な対応が、認知症とともに生きるご本人とご家族の生活の質(QOL)を維持し、より良い未来へとつながることを願っています。